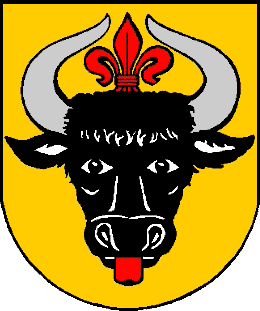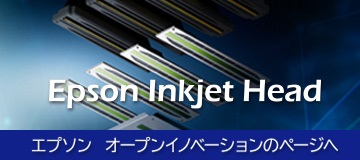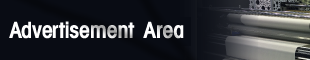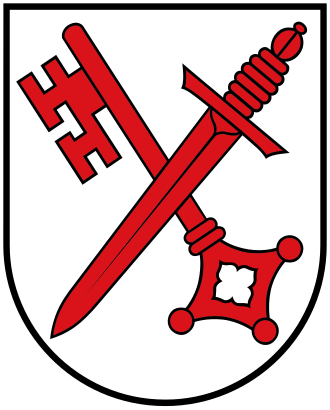- 2025-3-29
- ブログ
マルクト広場に Amtzturmが見えます。今は博物館になっているようです。風景は 1990年に見たものと基本的には変わっていません。ただ当時はどこも綺麗に整備された西ドイツと、補修資材が行き届かず崩壊寸前の家屋などが放置されていた東ドイツとの落差があまりに大きく、戦災での破壊を免れたこの町を見ても、第一印象としては「薄汚れた東の町」という色メガネをかけた印象の方が強かったのように思います。
今は、そういう状態からは一皮剝け、トラバントの排気ガスで薄汚れていた建物の表面もキレイになって、西側の町と遜色はありません。
ラートハウスは煉瓦造りの建物です。
独語 Wikipediaによれば「1224年には、この場所はルビチ(Lubicz)と呼ばれていました。その後、名称はルイゼ(Louize:1274年)、ルビチ(Lubicz:1317年)、ルビッツェ(Lubitze:1328年)、ルビッセ(Lubisse:1377年)と変わり、さらに短縮されてルビチェ(Lubcze:1322年)とルプツ(Luptz:1342年)となり、16世紀にはリューブツ(Lübz)となりました。この都市の古ポーランド語名は、この都市のスラブ系開拓者であるルベク(Lubec:ルベクの地)という個人名に由来します。 L’uby は「愛された」を意味するため、Lübz は「愛された都市」を意味します。 このように、この地名の語源はリューベック(Lübeck)のそれと類似しています」・・・とあります。
右の写真は 1990年のモノです。
よく見ると:
● Rathausの浮き文字の書体がちょっと違う
● その左手にある市の紋章の雄牛の絵柄がちょっとちがう(雄牛の顔と背景の色など)
● 1990年のにはその下に Lübzという町の名前があったが、今は無くなっている
● 扉が付け替えられている:1990年のには扉に窓が無いが、今のには窓がある
● 1990年は扉に向かって左手にランタンがあったが、今はそれは無くなり、そこに番地(Markt 22)のプレートが取り付けられている
・・・間違い探しではないですが、少しずつ変わっています。
目立ちませんが、煉瓦の表面が磨かれたのでしょうか・・・全体的にキレイに、明るくなった印象です。こういう地道な作業が町全体のの印象を変えるんですよね。
そういえば「Rathaus」と呼ばれる「市・町議会の場所(市・町庁舎)」は、旧東独では「Rat der Gemeinde」と呼ばれていたはずで、この「Rauhaus」の表示も妙に新しく、つい最近塗り替えられたように見えます。統一までもうあと3か月という時点で、フライングして「Rat der Gemeinde」を「Rathaus」に改称したのでしょうか?
ところで、この都市の紋章・・・ちょっとトボけた感じにも見える雄牛のアタマって、何なんですかね?左から:Lübz・Rehna・Mecklenburg-Vorpommern州・Ludwigsludt・Laage・Stavenhagenの紋章です。よく見ると「王冠を被り赤い舌を出した黒い雄牛のアタマ」ではありますが、よく見ると細部は少しずつ違っていますね。ちゃんと調べたわけではないですが、この州の半分くらいの都市や自治体にはどこかに使われている印象があります。
紋章に関する説明では「メクレンブルクの伝統的なシンボルは、皮のある、王冠を被ってにやりとしている雄の子牛の頭 (低地ドイツ語: Ossenkopp (“osse” は中央低地ドイツ語で「子牛」または「牛」。「牛の頭」の意) だが、起源はキリスト教化される以前の時代までさかのぼると言われている。このシンボルは、当時の人々が何を身にまとっていたかを表している。すなわち、雄の子牛の頭を帽子としてかぶり、日光から首を守るために背中へと皮をかけ、その姿全体でもって敵に恐怖心を与えていた」とあります。まあ、今となってはコワいというより、ちょっとユーモラスな印象ですけどね(笑)