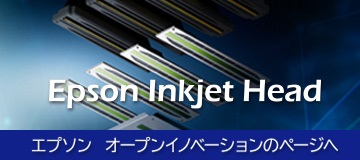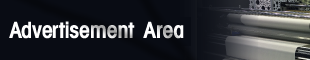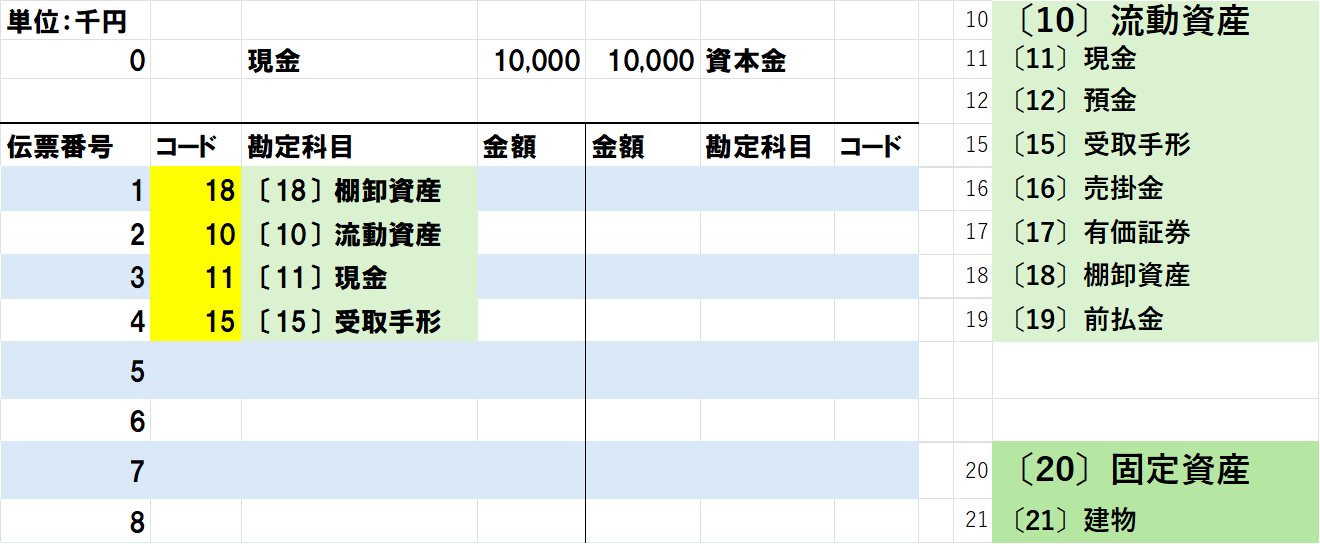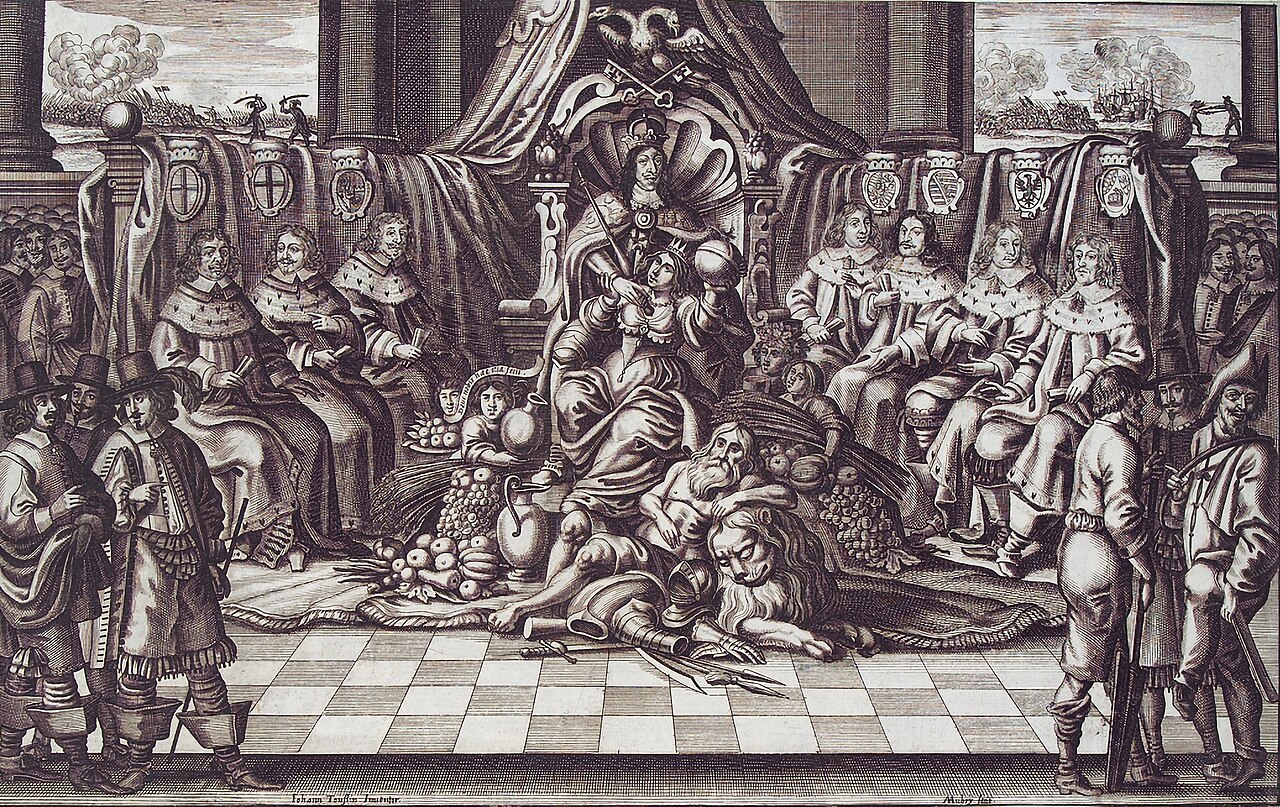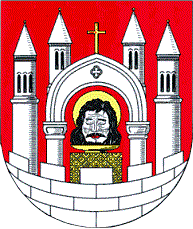- 2025-2-3
- ブログ
YouTubeからいくつか動画を拾っておきます。そして駅に向かいます。
Stadt Teterow Imagefilm Sommer 2013(約 3:00)
Willkommen in der Bergringstadt Teterow(約 1:30):短編の空撮動画
Teterow – Stadt im Mittelpunkt(約 10:00)
Besuch in Teterow DDR ca. 1960-1970 Farbe Verbesserte Qualität(約 8:40):東独時代の貴重な映像記録
Bergring Teterow – ZDF Dokumentation 1986(約 28:20)
マルヒン門(Malchiner Tor)を通って駅に戻ります
駅前の戦没者の墓地です
 いずれ纏めようと思っていますが、これまで記事にした町約80か所の他に、まだ記事にしていない30か所以上、そすてこれからまだ回るであろう数十か所の町をつぶさに見てきて、なんとなく町を見る・診る評価眼が定まってきたように感じています。その大きな切り口の一つは「この町は向こう20年間安泰なんだろうか?」ということです。
いずれ纏めようと思っていますが、これまで記事にした町約80か所の他に、まだ記事にしていない30か所以上、そすてこれからまだ回るであろう数十か所の町をつぶさに見てきて、なんとなく町を見る・診る評価眼が定まってきたように感じています。その大きな切り口の一つは「この町は向こう20年間安泰なんだろうか?」ということです。
確かに旧東独の町は、東西ドイツ統一後約40年近くの時を経て、多少の濃淡はありながらも政府からの復興予算を得て、見かけはかなりの修復が進みました。その一方で企業の倒産や廃業が相次いだ結果失業率が高まり、若くて移動が可能な世代を中心に少しでも良い職にありつける可能性のある大都市や旧西独への移動・移住が進みました。結果として今町に残っている層は高齢者が中心で、あと20年すれば絶滅する人たちが殆どです。謂わば「限界集落的都市」と言えるでしょう。
私が初めてドイツに赴任した 1980年代初頭の西独では、ドイツ人は郷土愛が強く地元で職を見つけるのが当たり前で、職の為に家族を犠牲にして単身赴任をする日本人って変な連中(笑)とみなされていたのです。が、それも探せば地元でまともな職がちゃんと見つかった豊かな時代の西独でのことでした。今の旧東独地域は地元にそんなものは無いのです。
そこに主として中東やウクライナなどの紛争地域から逃れてきた移民たちが住み始め、文化の様相も変わって来ています。ケバプ屋・ピザ屋・ベトナム料理やが安価な食を提供し、ドイツ料理屋やクナイペはどんどん廃業しています。余暇にクナイペに集まって仲間でスカットを楽しみながらビールを呑む・・・これは豊かだから可能なことだったのです。職が無くわずかな年金でその日暮らしをせざるを得ない高齢者達には、そういう余裕はありません。そうしてクナイペは客も減り、後継者も無く、廃業しか選択肢は無いのです。
こういう事情を踏まえて町を眺めていると、20年後の存在が危惧される町と、20年後も安泰に思える町がなんとなく見えてきます。人口10万人いればまあ何やら経済は回り、絶滅危惧度は下がります。20万人いればまずは安泰と言えるでしょう。問題は数多くの3万人以下の町です。観光資源に恵まれていればかなり安全度は増すでしょう。また「町の人の熱意・強いリーダーシップを発揮できる人」がいる町もいいと思います・・・が、人依存では所詮危ういので、そういう人をいかに継続的に生み出すかが肝になるように思います。
テーテロウの場合は、二つの城門だけでは観光資源としては十分とは思えませんが、Teterower Bergringというレース場、Burgwallinselを含む保養地の湖などを併せてかろうじてギリギリの観光資源はありますが、それに加えて恐らく町の人達(或いはその中心となる人)の熱意と郷土愛がいい状況を作り出しているように思えます。それは町が清潔に保たれていることや、中でも駅が廃墟化せず、ちゃんとリノベーションされて活用されていることでもわかります。こういう成功事例を他の「限界集落的」な町にも横展開でして欲しいものです。
五月の澄んだ青空に爽やかな風が吹いています
さて、この列車に乗って次の町へ行きます
★★★ テーテロウ Teterow の章を終わります。
シリーズ:誰も知らないドイツの町 Unbekannte deutsche Städte に戻ります。