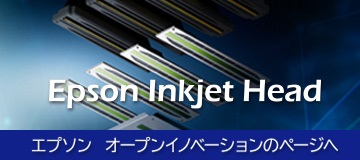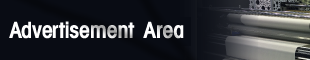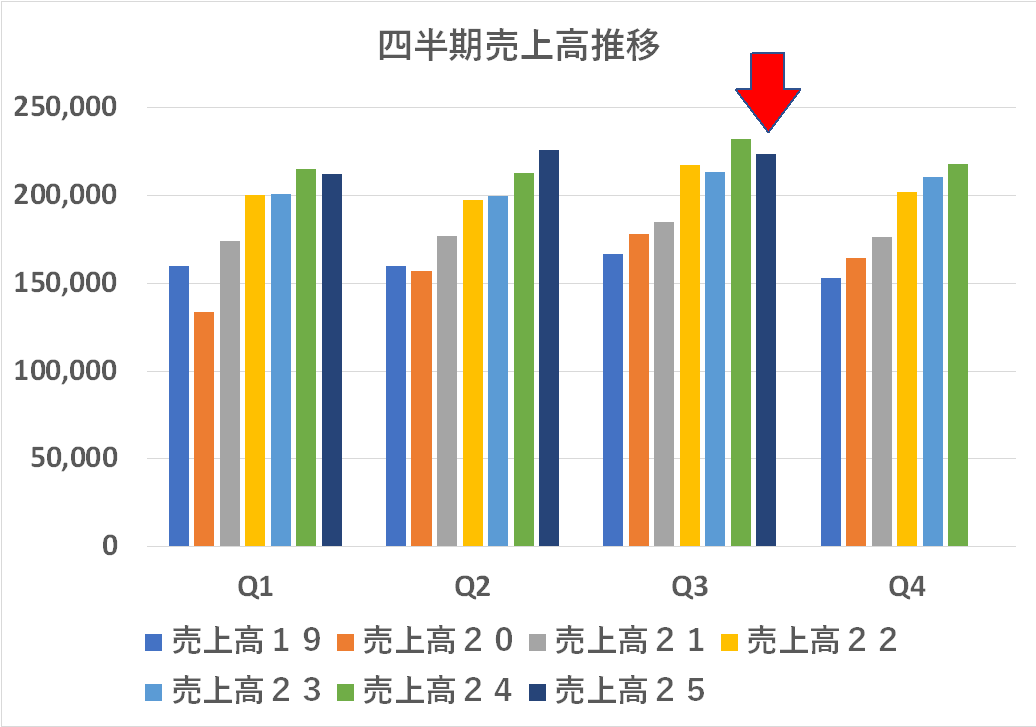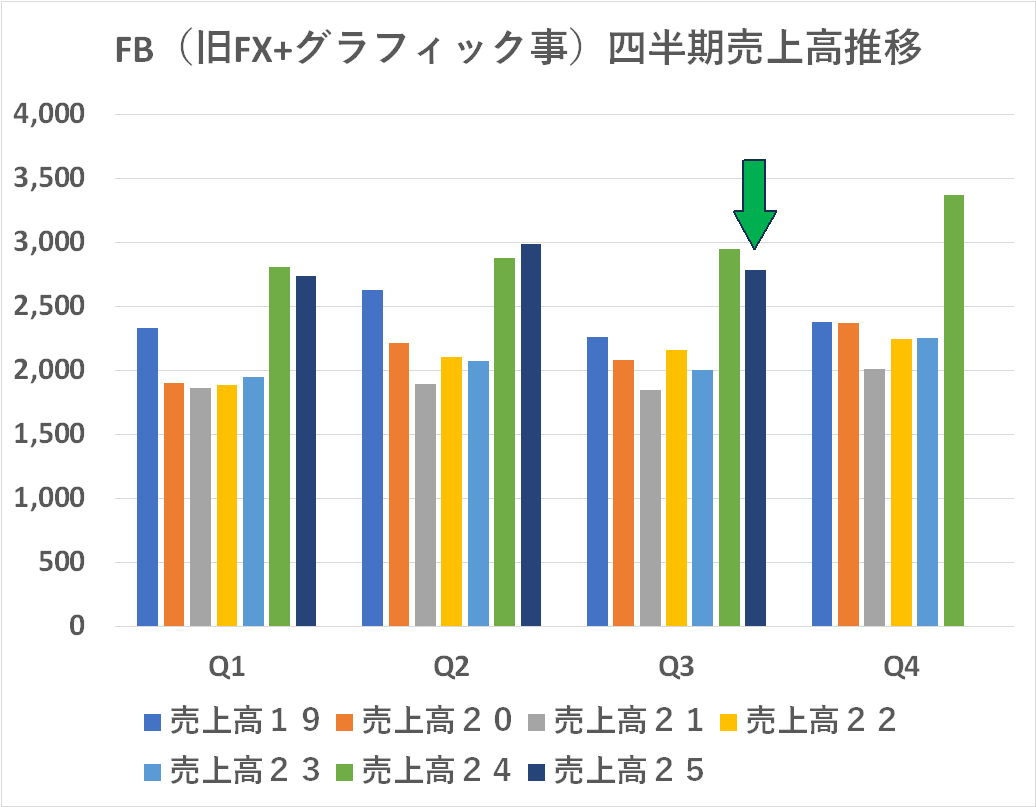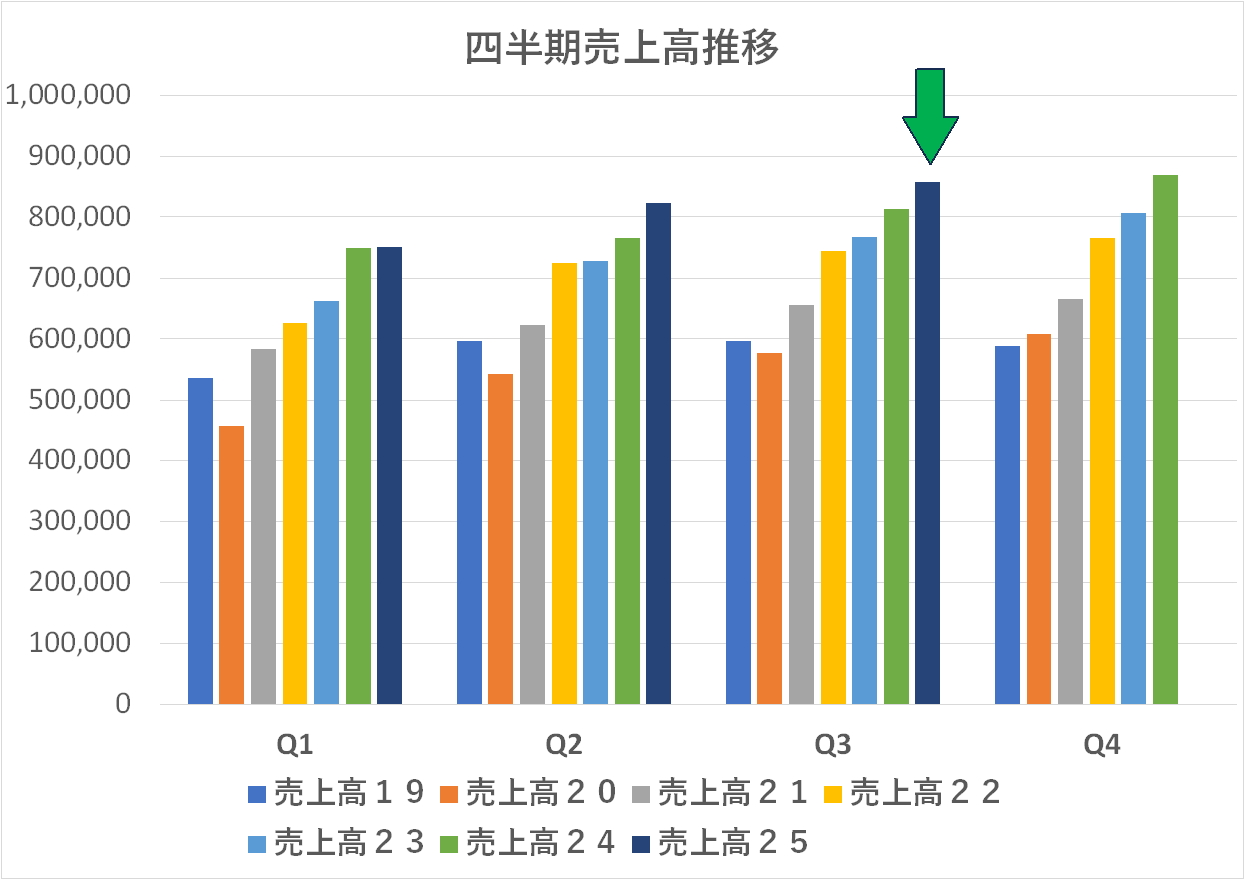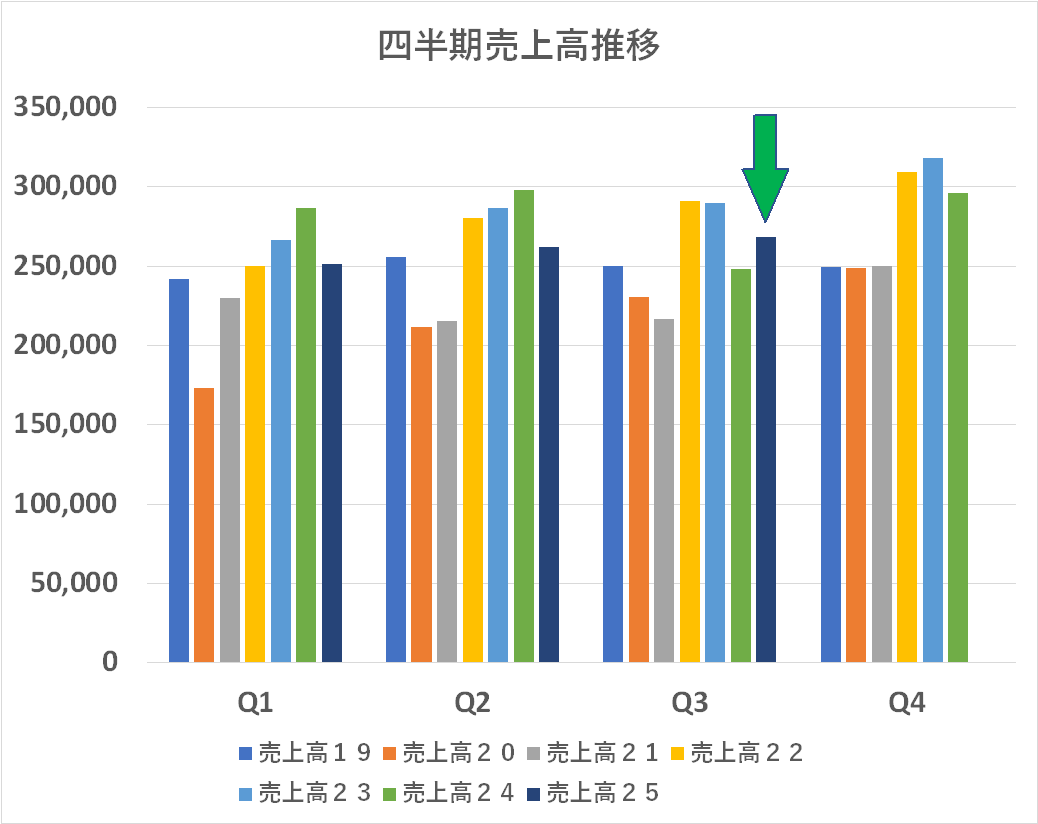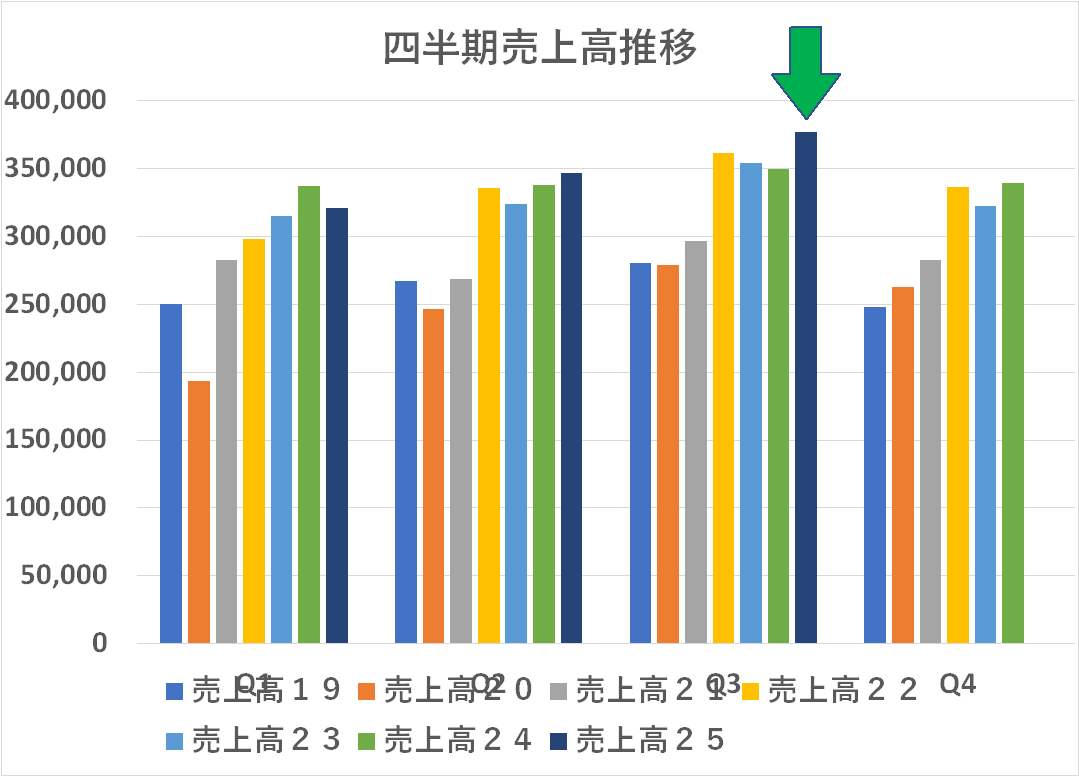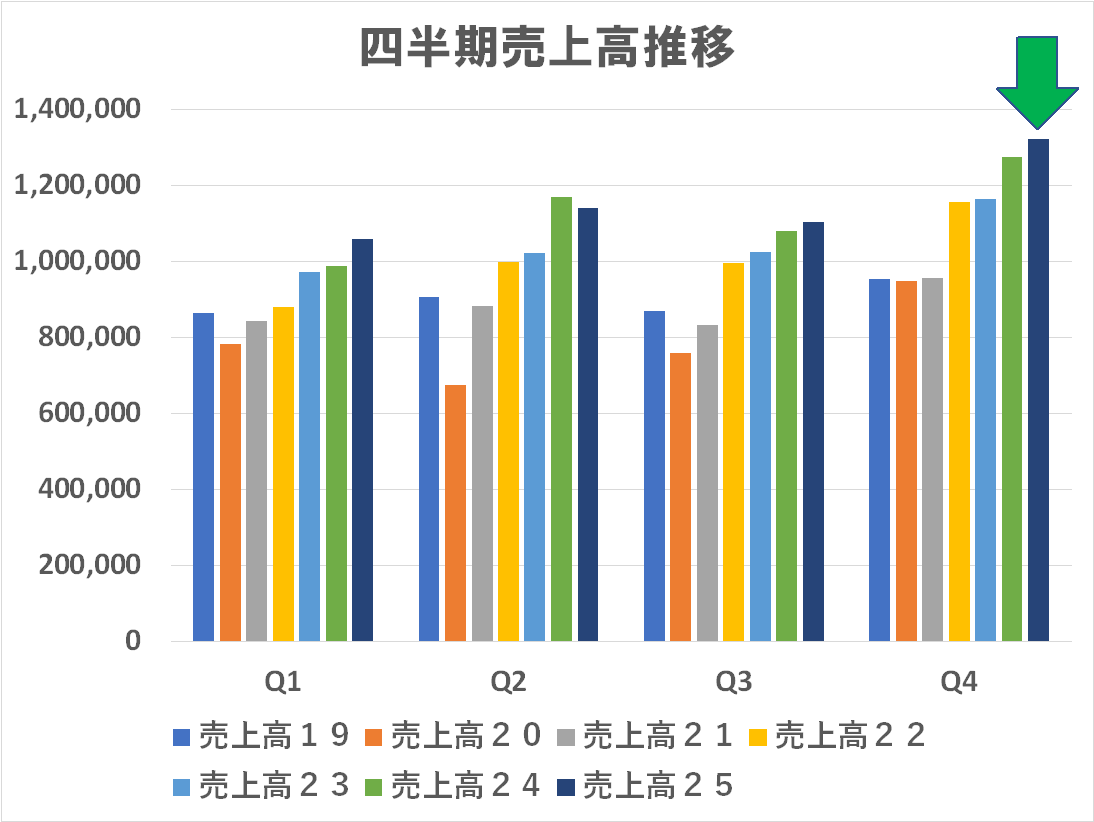- 2025-3-9
- トピックス
技術屋さんの皆さんは、中国企業から「開発を手伝ってほしい」とお声がかかった経験が少なからずあるのではないかと拝察します。特許や論文などで名前が売れていると、先方もそれを調べてお声を掛けてくる・・・普通にあることでしょう。
私は工学部卒ではありますが、インクジェットの技術屋としては全く活躍はしていないので、そういうお声の掛けられ方はありません・・・そりゃそうやな(笑)ただ、日本の産業用インクジェット界の「ドン」という認識はあるようで「だれか技術屋を紹介してくれませんか?」のようなことは実は数多くあります。
こういうのを、どう捌けばいいのでしょうか?ちょっと私見を書いてみます。
まず大きく分けて「ヘッドを開発したいので手伝ってほしい・技術屋を集めて欲しい」という話、「自分たちのプリンターのレベルを上げたい」「自分たちのインクの品質を上げたい」(それを手伝って欲しい)・・・という話があります。
私は「ヘッドを開発したいので手伝ってほしい・技術屋を集めて欲しい・紹介して欲しい」という話は絶対に受けません。
そういう話は実はたくさん来るのですが・・・まあ、日本にとってそこは最後の砦だろうというのもありますが、それよりもエプソンや富士フイルムやコニカミノルタや・・・そういう錚々たる日本メーカーが数百億円単位の投資をして今日があるインクジェットヘッド・・・これをちょっとアドバイスしたからと言って「コピー」が可能とはとても思えない・・・多分、手伝うと言ったらおカネは貰えると思いますが、結果として「できるという幻想を抱かせて、結果は出ない」ことに対しておカネを貰う・・・それは私の基本的な生きざまに合わないことなのです。
もし、日本人で「ヘッドの開発を手伝っている人」がいるとすれば・・・そこを今一度考えて頂ければと思います。
一方で、プリンターやインクに関しては考え方が異なります。
そもそもコニカミノルタで現役の事業部長時代に、中国のコニカミノルタヘッドユーザーのプリンターの品質のレベルを向上させるために「中国開拓団」と称したチームを作り、顧客の製品(=プリンター)のレベルを上げる活動をしていました。ヘッドは重要な部品ではありますが、結局はそれが搭載されたプリンターが売れなければリピートも何もないわけですね。ということで「コニカミノルタのヘッドは、ちゃんとプリンターが動くまでサポートしてくれる」という評判をゲットすることを目標としていました。
黎明期はそれなりの苦労はありましたが、結果としてはこのチームは、後任や新人などに人材の入換えはありつつも大変うまく機能したと思っています。あえてお名前を挙げますが、黎明期の開拓団メンバーだった山本さんや石橋さんは実に素晴らしい活躍をしてくれました。
インクに関しても、所謂「サードパーティ」インクメーカーを積極的にサポートしました。中国には「純正インク」という概念が実質存在しません。メーカーも「自社インクに縛り付けよう」というのは(無いとまでは言いませんが)実質的には放棄しています。ならばサードパーティインクメーカーを積極的に支援して彼らのインクのレベルを上げることはそれなりに合理性を持ちます。
コニカミノルタのヘッドが何故中国で評判がいいか?それは「どんなサードパーティインクを突っ込んでも、壊れることなくそれなりにちゃんと飛ぶ」というのがあった・あるからなのです。
ちょっと異なる視点ですが・・・日本企業には、退職した技術屋さんを縛る理由も正当性もありません。もしそれを主張するなら雇用延長して顧問なりアドバイザーなりでちゃんと処遇する必要があります。一部にはそういう技術屋さんもいるかもしれませんが、その対象外の方々は普通に「職業選択の自由」があってしかるべきです。それが中国に対してだけはダメで、韓国やアメリカや欧州企業ならいいのか?そんな理屈はありません。
どこかのパテントに触れるとかいうデリケートな話ではなく、一般的にインクジェットプリンターやインクの開発の基礎をちゃんと教えるには何の問題もないと考えています。
なおこの辺の一連の話はこちら(13ページ以降)をご参照ください。
もうひとつ・・・中国企業が「我々のプリンターを日本の品質にまで上げたいので手伝ってほしい」と頼まれます・・・これにはどう答えるのか?私は「おやめなさい」と言うことにしています。
日本の品質というのはちょっと優秀な技術屋さんがアドバイスや指導を行った程度で達成できるようなものではありません。まあ、それで7~8割くらいは品質が上がるという実感はあるかもしれませんが、残りの2~3割というのは例えば「品質に対する意識改革から始める」とか「開発とは独立した品質管理部門を作る」とか「不断・普段の現場改善・工程改善を行う」とか「自社だけではなく部品の納入業者にでかけて品質改善指導を行う」とか・・・そういうことが有機的に積み重なって達成されるもので、一朝一夕に達成できるものではありません。
一方で中国企業のよさもあります。「四の五の議論する前にまず手を動かしてみる」とか「議論する前にまず作ってみる、ダメならそこで考える」とか「70%くらいの完成度でもまず世に出してみて、そこからクレームや不具合報告を得て即改善する」とか「議論の為の議論に無駄な時間を費やさない」とか「決めるべき立場にある人が即決する」とか「品質確認会議のような『予定調和』的な儀式はやらない」とか・・・(笑)日本の品質に近づけようとすることで、逆に中国式の良さを失ってしまうことが考えられます。
ということで、私は「まずは日本の技術屋さんに会社や製品の成り立ちや現状を診断してもらい、直ぐに改善できることはすぐにやる。そこから先は、日本ジ技術者の基本的・理論に基づいた知見と、中国式のクイックな方法で目指すべき品質を一緒に創り上げていけばいい。間違っても形だけで日本の品質なるものをマネやコピーすることを考えないように!それがベストとは思えないし・・・」と言っています。
近々、この考え方に基づいて「中国開拓団パート2」を募集しようと思います!