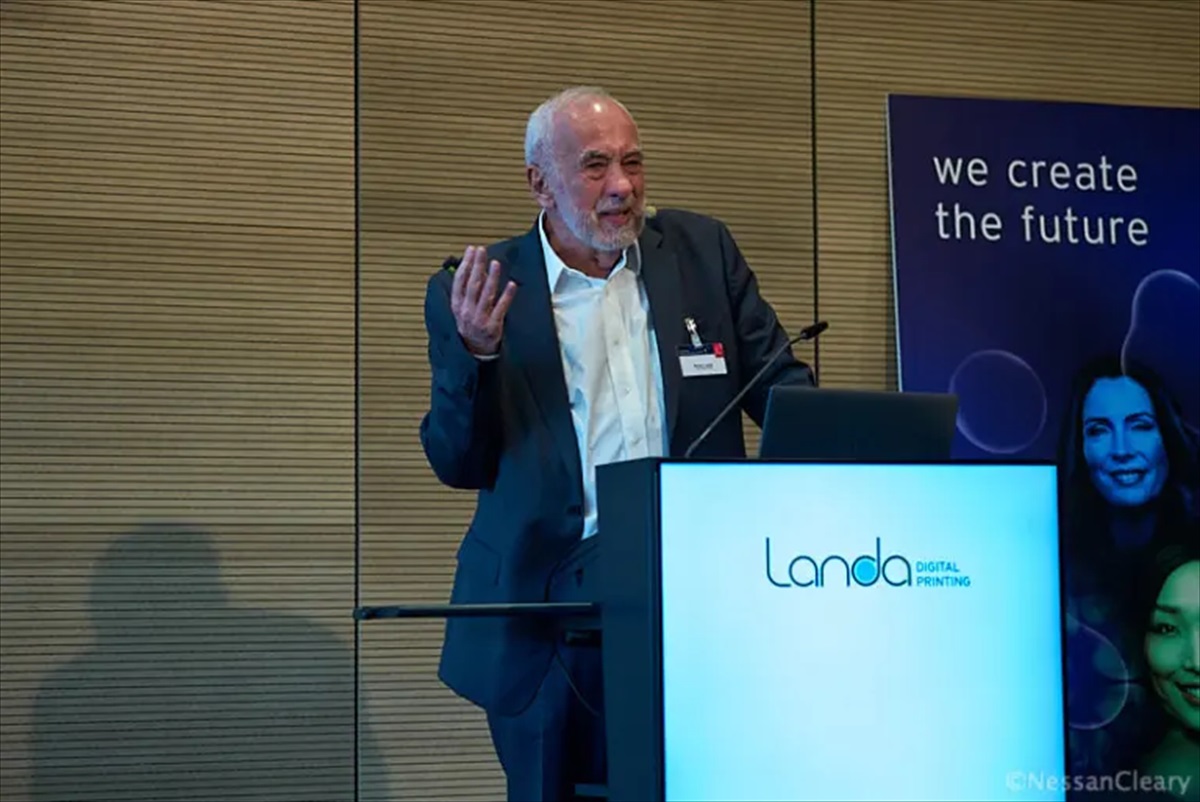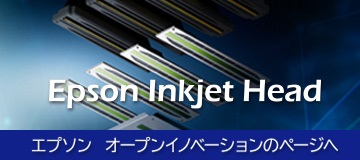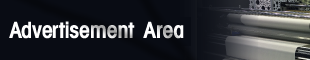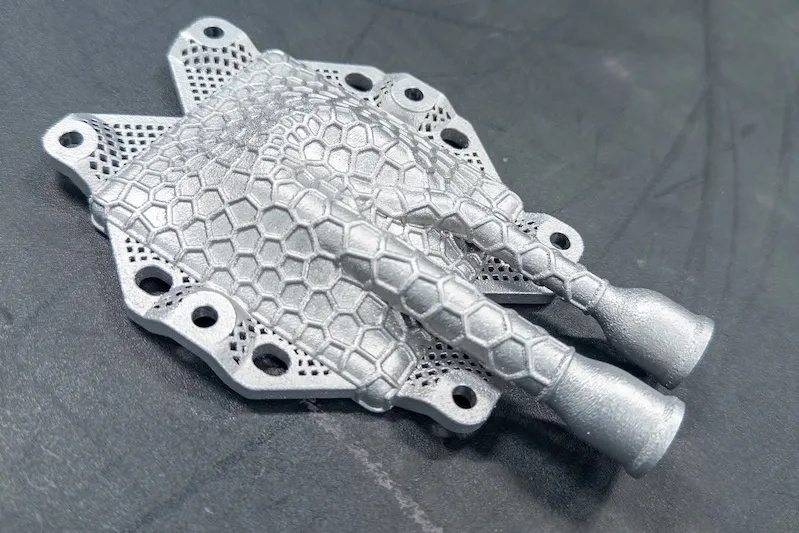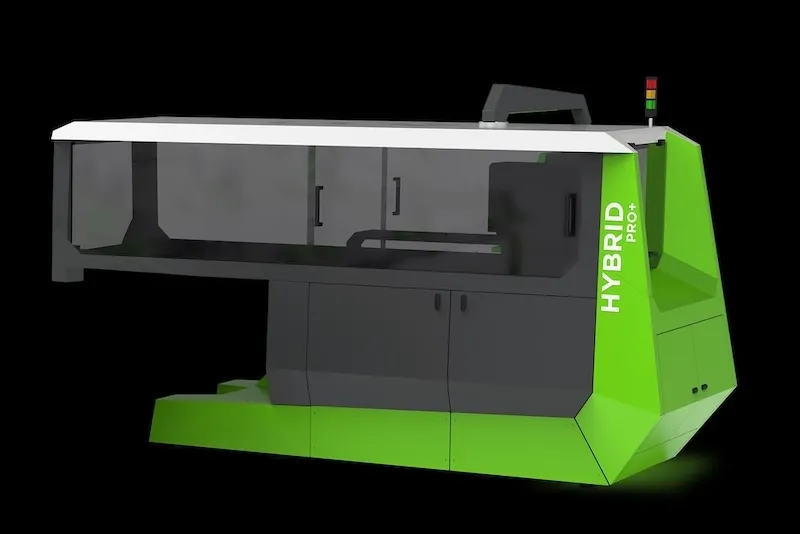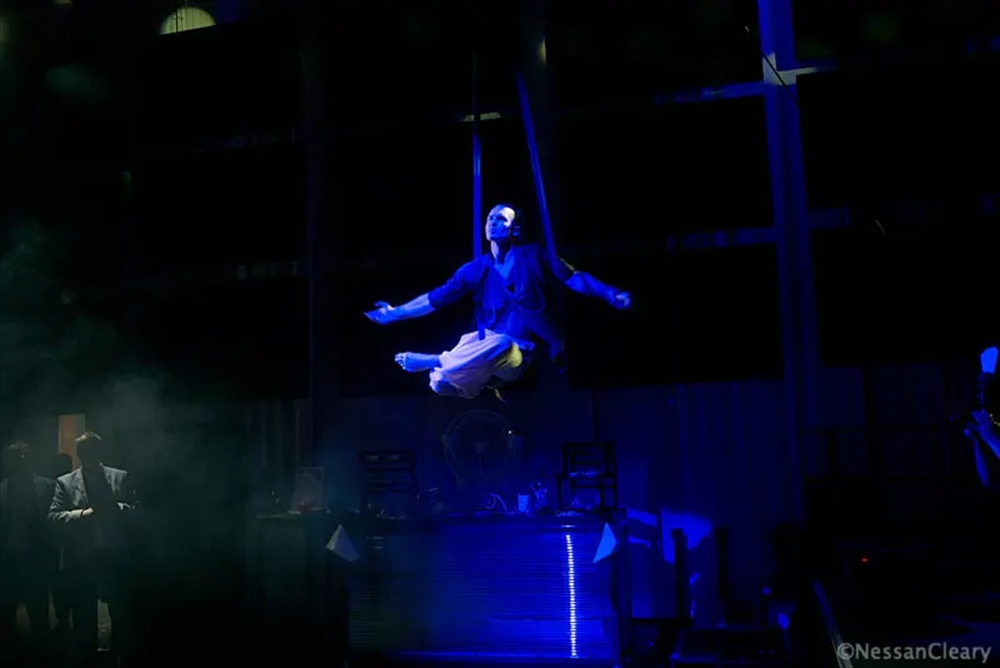- 2025-9-11
- Nessan Cleary 記事紹介
2025年9月11日
先週末、イスラエルの破産裁判所は、プライベート・エクイティ企業FIMIによるランダ・デジタル・プリンティング買収提案(8,000万ドル:約 120億円弱)を承認した。承認にはいくつかの行政上の変更が条件とされていたが、FIMIはここ数日でこれを完了させたため、本日 9月11日に取引が成立する見込みである。これにより FIMIは、全資産および特許を含むランダ・デジタル・プリンティングの単独所有者となる。
ランダ・ナノグラフィ技術と同社の破産申請については既に報じた。前回の記事では、裁判所が債権者への返済のために資産を売却する前に、ランダ・デジタル・プリント社が買収先を見つけるための 2ヶ月の猶予期間が与えられたと結んでいた。複数のプリンターメーカーが帳簿や技術自体を検討したとの憶測が飛び交ったが、結局入札を提出したのは FIMIのみであった。FIMIは、ランダ・デジタル・プリントを再編し収益性の高い事業体とした上で、約 3年後に売却することを目指すと表明している。
この買収提案が発表されて以来、大半の論評は「8,000万ドルではLDPの救済には全く不十分」との見解を示している。LDPの負債総額は 17億ドルに達し、FIMIによれば毎月さらに 1,200万ドルの資金を消費していたとされる。しかしランダの事例から浮かび上がったのは、投資家を無尽蔵の資金源と見なす財務管理の欠如だ。その典型例が、LDP取締役会が承認した地元開発業者ヴィタニア社への新本社ビル建設委託である。同社には不要かつ資金力も及ばないプロジェクトだった。建物は完成したものの、ランダ・デジタル・プリントは未だ移転していない。FIMIにとって幸いなことに、裁判所はこの賃貸契約を解除し、ヴィタニア社に 2億 2000万NISの頭痛の種を残した。
イスラエルに本拠を置く FIMIは、1996年にイシャイ・ダヴィディによって設立された。同社は様々な業界で経営不振企業の再生において極めて優れた実績を持つ。商業印刷の専門知識は持ち合わせていないが、イスラエルにはデジタル印刷を国際市場に販売するノウハウを持つ人材が豊富にいる。イスラエルの破産手続きは米国の連邦破産法第11章モデルを反映しており、債権者への返済のための資産処分よりも、企業の再編と存続を支援することを優先する。
合意条件に基づき、FIMIは主要サプライヤーへの未払い債務を全額返済する。ただし「主要サプライヤー」の定義には議論の余地があり、その他のサプライヤーには一部支払いとなる見込み。約 2,500万ドルが、これらのサプライヤーへの返済および従業員への未払い休暇手当等の債務返済に充てられる。
資金の一部は、最終的に他の投資家への返済を目的としたプールにも充てられる。ただし FIMIは、投資額を 1億6000万ドルに倍増させるまで、これらの投資家への返済を開始する必要はない。つまり、個人で2億ドルを投資したベニー・ランダは、返済対象となる債権者の中で最後の方となる。
残りの資金は、今後の会社運営資金に充てられる。ベニー・ランダは、少なくとも現時点では、創業者の肩書きと社名に彼の名前が冠されていること以外、同社とは一切関わりを持っていない。
ここで大きな疑問が残る。FIMIは本当にわずか 8,000万ドルで会社を立て直せるのか?ランダー氏の経営難に関する本記事及び過去記事の全情報源は、機密事項を自由に議論するため匿名扱いとする。(これは同時に、私の知性を実際以上に高く見せるという嬉しい副産物でもある!)とはいえ、ある情報源は「同社が黒字化に 3億ドル必要と報告した事実はない」と反論する。むしろ同社は破産手続き期間中も自力で運営できる十分な収益を上げていたという。
従来の債権者は 5月22日をもって同社への資金供給を停止すると取締役会に通告。その後 1カ月分の追加資金は提供されたものの、同社はこの日から借りた時間の中で生き延びていた。6月29日に破産申請を余儀なくされた際、裁判所が課した条件の一つに「新規債務の禁止」があった。つまり、従業員給与を含む継続的な事業活動に必要な収益を確保しなければならない状況だった。
最近の混乱期を通じて、LDPは顧客に対しインクやその他の消耗品、スペアパーツを供給できたため、顧客が稼働不能な印刷機を抱える事態は回避されたと聞いている。インクと一部の添加剤は12ヶ月の保存期間がありますが、混合後は3ヶ月に短縮されるため、大半の販売代理店は対応可能な在庫を保有していただろう。
この点は小森コーポレーションも確認済みであり、同社は顧客支援に十分な消耗品を保有している。私の理解では、小森とランダ間の日常業務は通常通り継続中だ。小森は印刷機シャーシと基材搬送装置を担当する重要サプライヤーであるため、同社への請求書は全額支払われるべきである。
また小森は自社製 NS40 B1印刷機向けにナノグラフィックインクジェット技術をライセンス供与しているため、消耗品の供給をランダに依存している。ランダ社は「小森とランダの顧客に差別はなく、全顧客に平等に供給する方針」と私に伝えている。小森は NS40を 3台設置済みであることを明らかにしており、内訳は中国に1台、日本の共進パッケージともう一社に各1台ずつである。
ある情報筋によれば、ランダ印刷機の印刷量は破産前と同水準を維持している。ただし、英国のブルーツリー社のように印刷量を最大化している顧客もいれば、主に高付加価値作業に印刷機を使用しているため比較的印刷量が少ない顧客もいる点に留意すべきである。したがって今後の課題は、全ての印刷機でより高い印刷量を確保し、LDPの消耗品収益を増加させることとなる。
憶測とは裏腹に、顧客は印刷機の代金を支払っていると聞いている。ただし、一部の印刷機では資金調達方法に差異があるとの認識だ。同様に、LDPは財政状況から、イスラエルからスタッフを派遣する代わりに現地販売代理店にサービス実施を依存せざるを得なかった。しかし、この方法は問題なく機能しており、今後は通常の手順として定着する見込みだ。
つまり FIMIは、プライベート・エクイティ企業が一般的に取る「基本に立ち返る」ビジネス手法が、LDPの財務基盤強化に十分有効だと見込んでいるようだ。ある情報筋が私に語ったように「FIMIは冷酷だが、会社を機能させられる可能性がある」 供給の継続性確保、印刷機の資金調達正常化、不要な間接費の削減がこれに寄与する。
FIMIが LDPの全従業員を継続雇用する可能性は示唆されているものの、その義務はない。むしろ、既存顧客をサポートする最小限の人員に削減される可能性が高い。印刷機の技術的側面の改善にはまだ課題が残されている。これにはブランケットの不均一性の解消やインクコスト削減が含まれ、一部の研究開発担当者の復帰を意味する可能性がある。
いずれにせよ、裁判手続きにより会社とその経営陣・取締役に対する追加債務は解消されたため、本日の取引で LDPのこの章は閉じられ、破産手続きに関連するさらなる法的措置は発生しない見込みだ。実質的に、裁判手続きにより過去の負債は清算され、LDPが新たなスタートを切る道が開かれた。
ベニー・ランダの経営スタイルについては多くの論評がなされるだろう。技術の過剰な誇大宣伝から会社の運営方法に至るまで、明らかに問題があった。しかし同時に、ランダが市場をリードする印刷技術を一つではなく二つも生み出した事実も忘れてはならない。確かにインディゴの安定化には HPの介入が必要だったように、今度は FIMIが LDPに対して同様の役割を果たさねばならない。それでもなお、これは重要な成果である。
当面の FIMIの優先課題は、コスト削減と既存顧客への継続的なサポート確保となる。近い将来に新たなランダ印刷機が発注される可能性は極めて低く、同社は現在稼働中の約 50台の印刷機からの収益で生き延びる必要がある。今年中にランダ社から新たな発表がある可能性は低いが、年末まで生き残ることができれば、この難局を乗り切れるかもしれない。
詳細については、landanano.com および fimi.co.il でご確認ください。